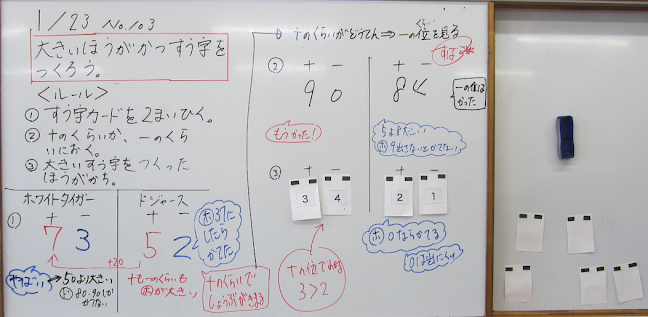子どもたちに,「5とびすごろくを作ろう」と投げかけます。既に100を超える数の学習は終わっています。そんな子どもたちに,0からスタートして120がゴールになる5とびのすごろく作りに取り組ませました。
5,10,15,20,25・・・の5とびの数の感覚や,5ずつ数が大きくなるに従って数値がどのように変化していくのかを実感させる目的があります。
数字には「やったね10すすむ」「ざんねん5もどる」などの,5を単位としたジャンプメッセージを追加することも可能としました。これにより,子どもたちは喜びながらすごろくを作成していました。ジャンプメッセージは単に指示を書くだけでなく,それに相応しい「弟におもちゃをあげた」「先生怒られた」などの文脈が併記されていました。子どもらしいすごろくができました。
この日は,すごろく作りで時間切れとなりました。次回は,これを使って遊びます!